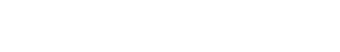RPAの運用ルールはなぜ重要?策定のコツや最適化のポイントを解説

RPA(Robotic Process Automation)は企業の業務効率化や生産性向上に大きく貢献するテクノロジーです。しかし、適切な運用ルールが定まっていない場合、トラブルや管理コストの増大などの問題が発生してしまう可能性があります。導入後に予期せぬエラーや想定外の動作が起こると、手作業でのリカバリーが必要になり、かえって負担が増えるケースも少なくありません。
この記事では、RPAの運用ルールが重要とされる理由や運用におけるリスクと、ルール策定から最適化までのポイントを分かりやすく解説します。何もルールを定めずに導入を急いでしまうと、“野良ロボット”の発生や誤処理を検知できない問題が顕在化する恐れがあります。RPAを長期的に活用して効率化を最大化するためにも、正しい運用ルールと継続的な見直しを行っていきましょう。
RPA運用の基本知識
RPA運用とは、開発したロボットを安定して稼働させ続けるための管理やメンテナンスを行うプロセスです。単にロボットを作って動かすだけではなく、誤作動があった際の対応、利用権限の調整、ソフトウェアやシステムのアップデートへの対応など、多方面の管理が必要になります。これらを適切に行うためには、あらかじめ運用ルールを定め、関連部署や担当者の協力を得ることが大切です。
また、RPA運用では業務手順の文書化やスケジュール管理、ライセンスの更新など、普段のIT管理とは異なる作業が求められる場合があります。特にRPAは既存システムとの連携が多いため、環境変更の影響を把握せずに放置するとエラーが連鎖する恐れがあります。これらのリスクを回避し、安定したRPA運用を継続させるためには、基本的な知識の習得と整備された環境づくりが欠かせません。
RPA運用とは
RPA運用とは、開発されたロボットが想定どおりに動作し続けるように管理し、必要に応じてメンテナンスや修正を加えることを指します。具体的には、実行タイミングの設定やエラー発生時のレポート手順の策定、ライセンスやサーバー管理といった多岐にわたる要素を含みます。運用体制が整っていないと、ロボットの誤作動やダウンタイムの長期化を招き、業務全体の効率が低下しやすい点に注意が必要です。
運用に必要な環境と準備
RPAの運用には、ロボットが稼働するサーバー環境や必要なライセンスの取得をはじめとするシステム的要件が不可欠です。また、業務上取り扱うデータの機密性に応じたアクセス制限や、ID・パスワードの一元管理など、セキュリティ面の整備も重要なポイントになります。さらに、RPA専任の担当者や監視体制を用意し、問題が発生した場合にすぐ対応できる準備を整えることで、安全かつ効率的な運用を維持することが可能です。
RPAの運用ルールを策定する重要性
効率化を進める一方で、見落としがちなトラブルや運用不備を防ぐために、ルール策定が欠かせません。
RPAを導入しても、その運用ルールが曖昧なままではシステム障害や誤作動の懸念を払拭しきれません。特に権限設定を行わないまま、誰でもロボットを作成できる状態であれば、いわゆる“野良ロボット”が増え、セキュリティリスクや運用コストの増大につながります。しっかりとルール策定を行うことで、トラブル防止と迅速な対応が可能となり、RPAの導入効果を十分に引き出すことができるのです。
また、運用ルールを定める過程では、開発や管理に関わる担当者も明確化しておく必要があります。誰が最終的な責任を負うのか、変更履歴はどのように追跡するのかを仕組み化しておけば、トラブル発生時の混乱を最小限に抑えられます。こうしたルールによって管理体制が強化されると、無駄な保守工数や追加開発の必要性が減り、結果としてコスト削減にも大きく寄与します。
RPAの運用ルールを策定する必要性について、3つの観点から解説します。

トラブル防止と迅速な対応
RPA運用中のトラブルを防止し、問題発生時の対応を迅速化するためには、運用ルールの策定が欠かせません。
RPAで自動化する業務の範囲が拡大すると、システムやプロセスが複雑化し、想定外のエラーやトラブルが発生する可能性が高まります。そのため、あらかじめエラー対応フローや責任の所在を明確に定めておき、問題発生時に迅速に対応できる環境を整えることが重要です。
運用ルールをしっかりと整備することで、トラブル発生時にも業務が停滞することなく、円滑に処理を進められます。
管理体制の強化
RPAでは、多数のロボットが同時に稼働するケースも少なくありませんが、権限管理や変更履歴の追跡が不十分だと、誤設定や不正活動を見逃してしまいます。
そこで運用ルールを定め、誰がどのロボットを管理するのか、ロボットに対する変更は何を根拠に実施されるのかなどを明確化することが不可欠です。管理体制が強化されれば、野良ロボットの発生リスクを大幅に抑えられ、長期的な安定稼働を実現できます。
コスト削減
運用ルールを定めることは、一見すると追加の手間に感じるかもしれません。しかし、ルールが整備されていないと、開発や保守のたびに過去の作業内容や担当者、設定情報の確認に時間を取られ、結果としてコストがかさんでしまうことがあります。適切に運用ルールを策定し、常に同じ手順でロボット管理を行えるようにしておけば、不要な工数を削減し、RPAの投資効果をより大きく高めることができるでしょう。
また、定期的な運用の見直しや改善策の導入もルールに組み込むと、無駄を省き、コスト効率を最大化できます。
RPA運用でよくあるリスクや課題
高い効果が期待できるRPAですが、適切な管理と運用がなされないと多様なリスクが顕在化します。
特に誤処理の検知が難しい状況や、管理者不在となってしまった野良ロボットの問題、既存システムとの不整合によるエラーなどは、対策を怠ると深刻な影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクを放置してしまうと、RPA導入による効果が損なわれるばかりか、オペレーション全体の混乱を招く原因となりかねません。特にロボットは人間と異なり、同じ手順を忠実に実行し続けるため、一度エラーを取り込むと連鎖的にミスが広がるリスクがあります。運用開始後も定期的に状態をチェックしながら、リスク回避策を講じることが重要です。
以下に、代表的なリスクや課題を中心に解説していきます。
誤処理を検知できない可能性
RPAでは、設定したとおりにロボットが動作するため、人間の目で確認する機会が減る一方で、誤りがあった場合に気づきにくいという問題が生じます。たとえば、誤ったデータを入力するようにロボットを設定してしまうと、ずっと誤情報を処理し続けるリスクがあります。これを防ぐためには、運用ルールの中に定期的な監視やサンプルチェックを組み込み、早期に異常を察知できる体制が必要です。
「野良ロボット」の発生
RPA導入後、誰も把握していないロボットが勝手に作成・稼働している状態を“野良ロボット”と呼びます。これは、管理者自身が導入していないロボットの稼働を把握できず、セキュリティリスクや想定外のトラブルを引き起こす大きな要因となります。運用ルールを徹底し、ロボット開発や稼働を許可制にするなどの対応によって、野良ロボットの発生を防止することが大切です。
こちらの記事もご参考ください→野良ロボットを生み出さないためのRPA運用とは?
既存システムとの不整合
RPAが業務の一部を自動化する際には、社内の既存システムとの連携が前提となるケースが多いです。しかし、アップデートなどによってシステムのUIや動作仕様が変わった場合、ロボットが動作できなくなったり誤作動を引き起こす可能性があります。
継続的に既存システムの変更情報を把握し、RPAを柔軟にアップデートしていくことで、こうした不整合による問題を最小限に抑えることができます。
RPA運用ルールを策定するための3STEP
RPAを安定して稼働させ続けるために必要な、3つのステップを紹介します。
しっかりと運用ルールを策定するには、まず開発フローの標準化や命名規則の設定といった基本ルールから始めることが重要です。次に、運用面のルールを細かく作り込み、運用を担うチームや担当者が迷わない仕組みを作り上げます。最後に、管理体制を確立して、ロボットの権限や変更履歴を含むガバナンスを継続的に維持・改善していくことが鍵となります。
この3つのステップを踏むことで、トラブル発生時の対応も円滑に行えるようになり、運用効率が大幅に向上します。特に、担当者の教育やマニュアル整備を計画的に進めることで、ロボットの開発・運用の品質を底上げし、結果的にRPAへの投資効果を最大限に引き出せるようになります。
1.RPA開発の基本ルールを定める
最初のステップは、開発の基礎となるルールづくりです。ソースコードの命名規則やバージョン管理の方法、テストプロセスの標準化などを決めておくと、開発段階でのミスを未然に防ぎやすくなります。また、ロボットが扱うデータや利用権限についても、開発時点で整理しておくことで、後々の運用管理がスムーズになります。
2.運用管理ルールを策定する
次に、ロボットが稼働するタイミングや条件、エラー発生時の報告方法など、運用そのもののルールを詳細に決めていきます。実行スケジュールや動作のトリガー設定が曖昧だと、想定外のタイミングでロボットが動いてしまい、システムに負荷をかけたり業務を混乱させる恐れがあります。また、エラー発生時にどのような情報を収集し、誰に連絡するのかを明確化することで、トラブル対応もスピーディーに行えます。
3.管理体制を整える
最後に行うのが、全体を統括する管理体制の確立です。具体的には、どの部署がロボットの開発・保守を担当し、問題が起きた場合には誰がリーダーシップをとるのかを決めておきます。さらに、各担当者がスムーズに運用できるよう教育プログラムやマニュアルを用意し、ロール分担と業務フローを文書化しておけば、担当者交代や新規メンバーの参加にも柔軟に対応できるようになります。
RPA運用を最適化するためのポイント
運用ルールの策定だけでなく、実際の運用品質を向上させるための取り組みに注目することも大切です。
RPAを導入するだけでは、必ずしも最大の効果を得られるわけではありません。運用を最適化するためには、部門間の連携やルールの標準化だけでなく、定期的に成果や課題を見直して再構築を図るプロセスが必要になります。それぞれの部署やプロジェクトが独自にロボットを改変してしまうと、後に統括管理が難しくなり、効果測定が困難になるケースもあります。
また、ベンダーやパートナー企業からのサポートを受けやすいRPAソリューションを選ぶことで、運用トラブルに迅速に対応しやすくなります。サポート体制がしっかりしていれば、システム変更時のアドバイスやエラー発生時の原因究明においても専門的な支援が受けられ、運用効率を大きく高めることが可能です。
部門間の連携を強化する
RPAの効果を最大限に引き出すためには、導入部門だけでなく、他の部門との連携も重要になります。特に、業務が複数の部門にまたがる場合、RPAによる自動化が他の業務にどのような影響を与えるかを共有し、全体としての最適化を目指す必要があります。
部門間のコミュニケーションを活性化することで、RPAの運用がスムーズに進むだけでなく、トラブルが発生した場合にも迅速な対応が可能となります。
連携を強化するためには、部門間にまたがる定期的なミーティングや情報共有の場を設けることが効果的です。部門間での連携が強まるほど、RPAによる業務効率化の幅も広がり、時間やコストの削減につながります。
運用ルールの標準化と文書化を徹底する
RPAを運用する上で見落とされがちなのが、ルールや手続きを明文化する作業です。ロボット開発時の命名規則やエラー報告のテンプレートを作成しておけば、担当者が変わったとしても運用品質が落ちにくくなります。標準化と文書化を徹底するれば、誰もが同じルールに基づいて作業を進められるようになります。
運用するメンバーが変わったとしても業務の一貫性が保たれ、エラーの発生率も減少します。全体の管理が容易になり、運用に関する情報を組織内でスムーズに共有できます。
定期的な運用見直しで最適化を図る
RPAは一度導入すれば終わりではなく、定期的に運用を見直して常に最適な状態を維持する必要があります。
導入当初は効率的であったプロセスでも、業務環境やニーズの変化により、改善が必要になるケースがあります。定期的な見直しにより、無駄なプロセスや不具合を洗い出し、必要に応じてプロセスを修正することで、運用効率をさらに高められます。
また、見直しの際には、実際に運用しているメンバーからのフィードバックを重視し、現場の課題を解決するための取り組みが重要です。
サポート体制が整ったRPAを導入する
RPAを効果的に運用するためには、信頼性の高いサポート体制が整ったRPAツールを選定することが大切です。
ツールの不具合や予期しないエラーが起こった時に、迅速に対応してもらえるサポート体制が用意されていれば、業務の停止時間を最小限に抑えられます。
また、サポート体制が十分に整備されているベンダーのツールは、アップデートや機能追加に関しても次々と最新の技術を取り入れていく傾向にあります。
RPAの導入時には、サポート内容や対応スピード、応対品質などを確認し、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。
運用ルールと体制を明確化し、「稼働状況と投資対効果」を見える化へ
RPAを効果的に活用するためには、運用ルールの明確化が不可欠です。明確なルールを設けることで、誤操作や不具合のリスクを減らし、効率的に業務を自動化できます。
RPAは複雑な業務を自動化できる一方で、運用方法によってはエラーや業務停止などを引き起こすリスクが伴います。そのため、導入前に運用体制を整え、ルールを明確化し、責任の所在やトラブル対応の手順を明らかにしておかなければなりません。
RPA運用の成熟度を高めるには、ロボットの稼働状況や開発・保守にかかった予算を詳細に把握し、費用対効果を常に検証することが欠かせません。管理と運用が明確になっていれば、どの部分を効率化すれば投資対効果がより大きくなるのか、定量的に分析できるようになります。
ユーザックシステムのRPA「Autoジョブ名人」は、稼働状況を見える化し、運用管理や投資対効果をきちんと把握できるRPAです。
最新バージョンに実装されたクラウド統合管理プラットフォーム「Pixis Cloud(ピクシスクラウド)」で、稼働状況やエラーをリアルタイムで把握し、業務の停滞や顧客対応の遅延のリスクを解消できます。
業務を安定的に自動化し、定着させれば、RPAの活用を全社的に拡大する見通しもつきます。人手不足や、属人化による業務の非効率に悩むことはなくなるでしょう。
Autoジョブ名人とPixis Cloudについてのお問合せやご相談は、資料請求かオンライン相談でお気軽にお申込みください。
関連記事
【RPA活用】シナリオの作り方とは?具体的なフローや注意点を解説
RPAを導入する際に重要になるのが、自動化のシナリオをどのように組み立てるかです。シナリオ作りのフローや注意点を理解すれば、エラーを最小化し、効果的に業務を自動化できるようになります。
記事はこちら→https://www.usknet.com/rpa/rpa_guide/34754/
RPAの無料トライアルで効率化を実感!活用シーンや導入フローを解説
無料トライアルを活用すれば、自社の環境に合ったRPAソリューションかどうかを事前に検証できます。具体的な導入ステップや活用シーンをイメージできるため、本格導入前にリスクを減らすことが可能です。
記事はこちら→https://www.usknet.com/rpa/rpa_guide/34709/
生成AI×RPAの活用法とは?できることやメリットを徹底解説
生成AI技術をRPAに組み合わせることで、一段と高度な業務自動化が期待できます。自然言語処理や画像認識などを活用し、対応可能な業務範囲が広がる事例について解説しています。
記事はこちら→https://www.usknet.com/rpa/rpa_automation/33738/
生産性向上にRPAが効果的な理由と活用事例5選を解説
生産性向上の手段としてRPAが注目される理由と、導入が成功した事例を複数紹介しています。具体的な成果が知りたい方にとって、取り組みのヒントとなるでしょう。
記事はこちら→https://www.usknet.com/rpa/rpa_guide/33732/
RPAの選び方とは?押さえておきたい6つのポイントを解説
ライセンス形態やサポート体制、拡張性など、RPA導入において確認すべき6つの要点をまとめています。自社のニーズに合った製品選定を行うために必見の内容です。
記事はこちら→https://www.usknet.com/rpa/rpa_guide/31456/
RPA開発は自社でできる?開発するメリットや手法・手順を解説
自社内でRPA開発を進めるメリットや、開発手法、実際のフローを詳しく紹介しています。外部委託と比較した際のコストやノウハウ蓄積など、検討材料として活用してください。