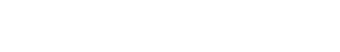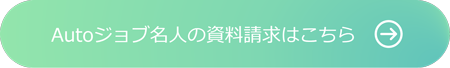RPAの使い方と気を付けるべきこととは?RPA活用を成功に導くポイント

RPA(Robotic Process Automation)は、定型業務を自動化するツールとして近年大きな注目を集めています。人手不足や働き方改革の流れも相まって、少ないリソースで生産性を高める手段として導入が進んでいます。RPAの基本的な使い方や運用のポイントを把握しておくことは、業務効率の向上だけでなくミスの削減や従業員のモチベーション維持にも直結します。
とはいえ、RPAを適切に使いこなすためには、導入前の準備や対象業務の選定、運用ルールづくりが欠かせません。やみくもに導入してしまうと、ロボットが想定外のエラーを起こして業務停止を招いたり、管理する人がいない“野良ロボット”が増えたりする可能性もあります。まずはRPAを使う目的や期待効果を明確にし、自動化の初心者でも安心して始められる手順を理解することが重要です。
本記事では、RPAで対応できる範囲や他の自動化ツールとの違い、実際の活用事例、導入時に気を付けたいポイントなどを詳しく解説していきます。RPAの使い方を正しく理解すれば、日々の業務効率化はもちろん、今後のビジネス展開に役立つ知見を得られるでしょう。ぜひ最後までご覧いただき、RPA導入の具体的なイメージをつかんでください。
RPAを使ってできることとその効果

RPA導入によって、どのような業務を自動化でき、その結果、どのような変化が期待できるのかを解説します。
RPAは日常的に繰り返し行われる定型業務を自動で代行するための仕組みです。例えば、システム間のデータ転記や請求書の発行、メールの送受信の整理などを人手を介さず処理できるようになります。企業によっては膨大な時間を割いていた単純作業が大幅に軽減され、生産性向上だけでなく残業時間の削減や従業員満足度の向上にもつながるでしょう。
また、RPAは人的ミスの減少にも貢献します。同じ操作を繰り返す処理はどうしてもヒューマンエラーが発生しやすい部分ですが、RPAに任せることで一定のルールに基づいた安定した処理が可能です。これにより、重要なコア業務へ人材を振り向けることができ、組織全体の業務効率を向上させる好循環を生み出すのです。
ただし、RPAの運用において手順書が曖昧だったり、頻繁に処理フローが変わる業務を無理に自動化しようとすると、かえってトラブルやメンテナンスコストが増えるケースもあります。導入前にきちんと要件定義を行い、RPAの特性を理解した上で使い方を設計することが大切です。
RPAでできることとは?
RPAは、ルールが明確でデータ処理の形が決まっている定型業務を自動化できます。具体的には、複数のシステムからデータを取得し、指定のフォーマットに整えて別のシステムへ入力したりレポートを作成するなどいった一連のプロセスが自動化できる代表例です。
また、PDFやメールの情報を抽出してExcelなどにまとめる作業も、一定のルールさえ定義すれば自動化が可能です。会計処理や受発注管理など、定型的な手作業が多い業務ほどRPAの恩恵を受けやすいといえます。
一方、判断や複雑な意思決定を伴う業務はルール化が難しいため、RPAには向きません。事前に、RPAの活用範囲かどうかを見極める調査(業務の棚卸)が重要です。RPAでの自動化に向く適切な業務を選ぶことで、スムーズな導入と安定運用が期待できます。
RPAを使うことで得られる効果
RPA導入により得られる最大のメリットは、時間や手間がかかる単純作業から人材を解放できることです。特に繰り返し作業を行う業務では工数削減効果が高く、浮いた時間をコア業務の時間や予算を手厚くすることが可能になります。
あらかじめ決めたルールに則って作業を自動化するので、人間と比べて作業品質のばらつきがない点も大きなポイントです。ヒューマンエラーが多い領域にRPAを導入すれば、ミスによる手戻りやクレーム対応などの負荷を低減できるでしょう。
これらの効果は、現場の担当者だけでなく企業全体の競争力強化にも寄与します。生産性の底上げが、働き方改革や新しいサービス開発など、周辺領域への投資や挑戦を後押しする原動力ともなっていきます。
RPAと他の自動化ツールとの違い
RPAは、Excelマクロや専用プログラムによる自動化と比較されることが多いですが、その大きな特徴の一つは“複数アプリケーションにまたがる操作をまとめて自動化できる”点にあります。たとえば、ウェブシステムからの情報取得と基幹システムへの入力をワンストップで完結できることがRPAの強みです。
AIと組み合わせる事例も増えていますが、AIが判断を担当し、RPAが具体的な処理を実行するといった役割分担が主流です。AIが曖昧なデータの解析や学習を担い、RPAが定型化した操作をこなすことで、ビジネス価値を高めることができます。
こうした幅広い自動化範囲をカバーできる一方で、RPAツールの設定や管理にはある程度の知識が必要になることも事実です。導入前に、どこまでをRPAで処理して、どこからを他のツールや人の判断に任せるのか、明確に方針を定めておく必要があります。
RPA活用を成功に導くポイント
RPA導入で大切なのは、仕組みを導入するだけでなく、継続的に運用していくための体制づくりです。
まずは現場における定型業務を見える化し、自動化に適した業務を抽出することから始めます。複数部署にまたがる作業がある場合は、RPAから得られる相乗効果が大きいケースもあるため、部門横断的な視点で考察すると効率的です。
次に、導入の段階から運用フェーズまで一貫して管理できる体制を整えることが重要です。万が一の不具合が生じた際の対応ルールを明確にしておかないと、RPAがエラーで止まってしまった場合、業務に大きな支障をきたすリスクがあります。
導入後は、定期的にロボットの動作状況をチェックし、業務フロー変更やシステムのアップデートに柔軟に対応してください。運用ルールを細かく決めておけば、“野良ロボット”が発生することなく、RPAの導入効果を長期的に得られるしょう。
RPAを使った成功事例3選

RPAの導入を検討する中で一番気になるのが、RPAを使って具体的にどのように目的を達成したかということではないでしょうか。
ここではユーザックシステムが提供するRPAツールを導入し、実際に自動化・効率化に成功した企業の事例を3つご紹介します。
POSデータのダウンロード作業を⾃動化
酒造メーカーとして有名なサッポロビール株式会社様は、2016年にブラウザの操作を自動化するソフト「Autoブラウザ名人(現・Autoジョブ名人)」を導入し、これまで人の手で行っていたPOSデータのダウンロード作業の自動化に成功しています。
サッポロビール株式会社は、在庫管理や購買行動の把握のためのPOSデータのダウンロード作業が必要でした。PRA導入以前の人の手で行っていた時には、一つの企業からPOSデータの取得するのに20~30分もの時間がかかっていました。
POSデータのダウンロードは毎日・毎週行う必要があり、対象企業が増えるにつれて手作業での遂行には限界があると考え、RPAを使って自動化することを決断しました。
導入後は平日朝8時になると自動的にRPAが起動し、対象企業のWebサイトにアクセス、順次POSデータのダウンロードを開始してくれるようになりました。14時30分頃には全社の全カテゴリーのPOSデータを自動的に取得し終えるため、運用1年で一人分の人件費とペイすると試算できており、費用対効果の高さを感じているとのことです。
2ヶ月のトライアル期間で業務効率向上を実感
バイク便事業を展開する株式会社セルートは、輸配送の注文を受けるごとに増加する「受発注者情報の処理業務」の課題解決のため「Autoジョブ名人」を導入し、自動化によって業務を効率化することに成功しています。
「受発注者情報の処理業務」は経理グループが担当していましたが、複雑な作業内容と手作業の多さが業務進行を鈍化させていたため、RPAの導入が選択肢に挙がりました。
それまではパターンに応じて、各伝票を請求処理に回すか、売上処理で終了するか、支払処理につなげるかなどを社員が1件ずつ仕分けしていました。RPA導入による自動化の後は、Excel上の修正が発生していないデータについては「Autoジョブ名人」に自動でOKボタンを押してもらい、それ以外の修正作業といった人の手が必要な作業のみ、従来の担当者が仕分けする効率的な形に変化しています。
「RPAの導入費用は導入月に元が取れた」と株式会社セルートは語っており、「Autoジョブ名人」のトライアル期間(無料お試し期間)で、すでに業務効率向上に効果を実感することができました。
Webからの受注処理を自動化
焼肉のたれをはじめとした調味料・調味食品を製造・販売するモランボン株式会社は、2018年4月に社内のあらゆるブラウザを自動化するRPAツール「Autoブラウザ名人(現・Autoジョブ名人)」を導入し、災害などによる作業ストップの回避を目的とした自動化を達成しています。
モランボン株式会社が災害などによる作業ストップへの対策を意識するようになったのは東日本大震災がきっかけでした。当時、計画停電によって4~5時間の間社内の作業がストップしてしまったことが、安定的な運用体制を構築する理由となったそうです。
現在は自社内で独自に構築していた基幹システムをオープン化し、サーバーもすべてデータセンターへ移行、BCP対策に則った運用体制で災害リスク回避ができる状態にしています。
RPAの導入により、受注業務などのいくつかの業務が自動化され、担当者の負担減と人的リソースの確保を実現しました。人事、総務、マーケティング分野といった別部門でも、業務の自動化を増やしていく計画をしています。
RPAを使う上で気を付けたいこと

効果的な運用とトラブル回避のために、導入時から意識しておきたいポイントを示します。
RPAは導入するだけでは期待通りの効果が得られない場合があります。勝手にロボットが動き続けると想定して放置すると、エラーや仕様変更への未対応で停止するリスクが高まるからです。導入の段階から保守や管理の役割が明確に決められているか確認しましょう。
また、RPAに任せられない業務を把握することも大切です。複雑な判断や最新の情報をもとに動きが変わるような業務は、人間が最終チェックを行う仕組みを残しておくべきです。RPAで自動化できる範囲をしっかり見極め、使い方を工夫することで安定した効果が得られます。
さらに、導入後も定期的に業務プロセスを見直していく姿勢が必要です。業務フローが変わる際はRPAのシナリオ修正を速やかに行わないと、せっかくの自動化体制が機能しなくなる恐れもあります。
目的を明確にする
RPA導入のゴールをはっきり設定しておくことが重要です。コスト削減や労働時間の短縮、業務の正確性向上など、期待する効果を定量的に把握し、社内で共有することでプロジェクトの進む方向性が一貫します。
目的が曖昧だと、不要な業務まで自動化しようとしてシナリオが複雑化したり、逆に効率のいい業務改善を見逃してしまう恐れがあります。初期段階で明確な目標を設定することが、長期的な成功に直結します。
全員がRPAの導入理由を理解できていれば、導入後の運用中も継続的な改善につなげやすくなります。チーム全体で共通認識を持つことは、RPAプロジェクト推進における基盤作りといえるでしょう。
自動化できる業務の棚卸
RPAの効果を最大化するには、自動化の対象として適切な業務を選ぶ必要があります。あらゆる業務を一度に棚卸しし、処理頻度や定型化の度合い、エラー発生リスクなどを指標として優先順位をつけておくとよいでしょう。
棚卸を行うことで、意外な作業が多くの時間を奪っている実態が明らかになる場合も少なくありません。こうした業務をピンポイントでRPA化し、結果を素早く出すことで社内での導入支持を得やすくなります。
ただし、業務全体を常に見える化し、変化が起きた際にすぐに対応できるような体制も必要です。棚卸と運用管理を両立させることで、RPA導入によるメリットを途切れさせない運用が実現できます。
エラー時に対応できるようにする
RPAが想定外のエラーを起こす可能性はゼロではありません。特に、外部システムの仕様が変更されたり、手動操作が加わったりするとそうしたリスクが高まります。
そこで、エラーの検知方法や対応手順を事前に整備しておくことが大切です。例えば、RPAが動作を停止したときにアラートを発する仕組みを用意し、原因を調査する担当者を決めておけば、大きな混乱を防げるでしょう。
また、予想しやすいエラーに関しては、サブルートを設けるなど柔軟に対応できるシナリオ設計を行うのも有用です。早期発見と素早い復旧の体制が、RPAを長く安定運用するための鍵となります。
RPAの開発・運用に不安がある場合は、サポート体制が充実したRPAツールを選択すると安心です。ユーザックシステムが提供するRPA「Autoジョブ名人」は、カスタマーサクセスプランナーによるサポートメニューや、ユーザーコミュニティが充実しています。くわしくは下記の記事もご覧ください。
スモールスタート
RPAを導入し始める際には、スモールスタートで着実に成果を出す方法が勧められます。まずは小規模な範囲で自動化を試して、問題点や改善点を洗い出すのが安全策です。
いきなり大規模に展開すると、初期費用やシナリオの作り込みが膨大になりがちで、途中段階のトラブル対応に追われてしまう可能性があります。段階を踏んでRPAの扱いに慣れながら進めることで、適切な運用体制を築けます。
スモールスタートでは、効果が短期的に見込める業務を選ぶと社内での導入評価も得やすく、成功体験が次の自動化領域拡大のモチベーションになります。小さく始めて、大きな成果を目指すことがRPA導入の定石と言えるでしょう。
まずは無料トライアルを検討しよう

初期投資を抑えながらRPAの実用性や効果を検証するには、無料トライアルの活用がおすすめです。
RPAを導入するうえで、最初から有料ライセンスを取得するのはハードルが高い場合があります。そこで、多くのRPAベンダーが提供している無料トライアルやデモ版を活用すると、導入前に自社の業務に合うかどうかを試験的に検証できます。
無料トライアルを利用すれば、RPAツールの使いやすさやサポート体制を確認できるだけでなく、具体的にどの程度の時間削減やエラー減少が見込めるかを社内で共有しやすくなります。結果として、意思決定のスピードアップや導入リスクの低減につながるのです。
また、実際のトライアルを通じて発見した技術的・運用面的な課題をクリアしやすい点もメリットです。短期間でも現場で動かしてみることで、RPAロボット開発の手順や必要な管理体制を具体的にイメージできるでしょう。
「Autoジョブ名人」は、お客様専属のカスタマーサクセスプランナーによる業務効率化のアドバイスを受けながら、無料トライアルをお試しいただくことができます。
トライアル期間中にRPAの効果を実感していただき、RPA導入後の投資対効果の見通しをつけた状態で、計画的な業務自動化プロジェクトを推進していただけます。RPAによる業務効率化をご検討であれば、下記のリンクからお気軽にお申込みください。
関連記事
より幅広い活用方法や導入ステップを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
RPAを使い、社内で運用し続けるには、定期的なルールの見直しや技術のアップデートに合わせたシナリオ修正が不可欠です。ここでは、RPA活用の背景や導入後のメンテナンス、具体的な事例などを掘り下げた関連記事を紹介します。
それぞれの内容を比較しながら読むことで、自社に合った導入ステップや運用スタイルのヒントが得られます。今後のRPA展開を検討している方も、ぜひ一度目を通してみてください。
RPAの運用ルールはなぜ重要?策定のコツや最適化のポイントを解説
運用ルールが曖昧だと、想定外のエラーやシステム変更への対応が後手に回る恐れが高まります。この記事では、RPAの運用ルール策定に必要な考え方や運用監視の最適化ポイントを紹介します。
あらかじめロボットのバージョン管理やシステム改修時の体制を決めておけば、実際に問題が起こった際に迅速に対応できるでしょう。運用ルールの整備が、長期的な業務効率の維持に直結します。
ルール自体も継続的に更新し、現場のフィードバックを反映させることで実効性を高める方法を解説しています。常に最新の業務フローと合致したロボット運用を維持するために、ぜひ一読してみてください。
RPAは単純なデータ入力やファイル操作だけでなく、多様なシステム連携にも対応可能です。この記事では、RPAで実際にどのような業務が自動化できるのか、より詳しい例を挙げながら具体的に解説します。
導入メリットとしては、作業時間の大幅削減やミス削減だけでなく、社員のモチベーション向上や離職率低下などの二次的効果も取り上げています。事例を通じて成果をイメージしやすい内容です。
企業規模や業種を問わず活用できるヒントが盛りだくさんなので、RPAに興味がある方はもちろん、すでに導入している方にも役立つトピックが揃っています。
RPA開発は自社でできる?開発するメリットや手法・手順を解説
RPAを外部委託するか、内製化するかは企業のスタンスによって異なります。この記事では、自社でRPA開発を行うメリットや進め方、必要なリソースなどを紹介しています。
内製化を行えば、システム変更や業務フローの改編にも柔軟に対応しやすくなります。一方で、開発担当者のスキルアップやメンテナンスフローの整備が必要不可欠になる点も注意が必要です。
特に、迅速な問題解決や新規業務への対応を重視する企業では、自社にノウハウを蓄積することが大きな強みになるでしょう。運用管理まで含めたトータルの手法を理解することで、RPA開発のハードルを下げることができます。
RPA化=業務効率化への近道って本当?メリットや事例を詳しく紹介
一般的にRPA化は業務効率化の近道といわれますが、一部では「自動化そのものが目的化してしまう」という失敗も報告されています。この記事では、そのようなリスクを回避しながら効率化を実現する方法を紐解きます。
特に、定型業務以外にRPAを拡張した事例なども取り上げ、メリットだけでなく可能性と注意点の両面から検証しています。成功事例を多数紹介しているので、自社の参考になるケーススタディが見つかるでしょう。
RPAツールを選定する段階で押さえておくべき要件や、運用ルール策定のコツなども解説しているため、導入検討の入り口から運用改善までを俯瞰できる内容です。
RPA導入を成功させる鍵は、しっかりと計画されたステップを踏むことにあります。この記事では、事前準備、ツール選定、シナリオ作成、運用体制構築などを段階的に解説します。
それぞれのステップでありがちなつまずきポイントや回避策も併せて紹介しているため、初めてRPAを導入する企業でも大きな失敗を防ぎやすいでしょう。
具体例が豊富なので、実運用に近いイメージを持ちやすく、現場の担当者や経営層とのコミュニケーションにも役立つ内容です。導入後のトラブルを未然に防ぐためにも、事前に目を通しておくことをおすすめします。